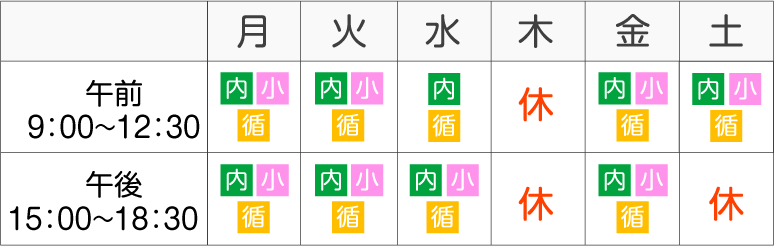- 花粉症とは
花粉症は、植物の花粉を抗原とする
アレルギー性鼻炎 の一型です。日本では主に スギ(2–3月)、ヒノキ(3–4月)、イネ科(初夏)、ブタクサ(秋)が原因となります。
症状はくしゃみ、水様性鼻汁、鼻閉、眼のかゆみ が典型です。
花粉症の一般的なお話しはインターネット上で詳しく出ているのでそちらをお読みください。
わかりやすく書いてあるサイトをご紹介します。
花粉症のはなし ~原因とメカニズム~|アレジオン【エスエス製薬】
- 診断について
症状に季節性があることが診断に重要で、スギであれば2-4月、ヒノキであれば4-5月に症状が限定されればかなりの確率で特定できます。鼻内の蒼白腫脹の所見もアレルギー性鼻炎を示唆するものです。血清特異的IgEは血液で簡単にアレルギーがあるかどうかを調べる簡易的な方法で内科でもよく行われています。これでスギが陽性ならスギ花粉症であることが判明します。但し陰性でも、季節性の鼻炎がはっきりしていて、抗アレルギー薬が効けばスギ花粉症の可能性は残ります。IgE値の感度は100%ではないのです。ここで得られた特異的IgEの値は症状の重症度とは異なりますので注意が必要です。
- なぜ患者が増えているのか? 東京と隣県との違い
都内の花粉症保有者は10年前の統計ですが、その30年前と比較して4-5倍に増加し、10-20代では約60%の人が花粉症と言われています。
考えられている要因
- 大気汚染説
スギ人工林の増加、都市部の大気汚染、衛生仮説(微生物曝露減少)、生活様式の変化などが考えられています。特にディーゼル排気微粒子はアレルギー反応を増強すると報告されています。東京都は千葉県より単位面積当たりのスギの本数が少ないのに花粉症人口は多いこともこの仮説が有力であることを示しています。
東京都では多摩地域を中心に花粉の少ないスギの木に植え替える事業が進行中とのことですが、併せて環境保全も重要ということですね。
- 衛生仮説
幼少期の清潔志向により免疫制御系のTh2活性が高まり、IgE抗体の産生が促される結果、ヒスタミンなどのアレルギー物質を産生する肥満細胞が活性化され、花粉症を引き起こすと言われています。最近は新型コロナ感染やインフルエンザの予防のためより清潔志向が高まっていますが、子供たちの将来が心配ですね。
5.治療
① 薬物療法
第2世代抗ヒスタミン薬、点鼻ステロイド、ロイコトリエン受容体拮抗薬。飛散前から開始することでピーク症状を抑制できます。
抗ヒスタミン薬は薬局で購入することもできます。
重症例では併用療法が有効ですが、医療機関と相談してください。
また、重症例で注射薬があります。抗IgE抗体薬であるオマリズマブ(ゾレアⓇ)という薬です。
この薬を2-4週間に1回注射します。この注射は誰でも使えるわけではないので希望者は医療機関と相談してください。ゾレアについて | 花粉症の注射
③ 舌下免疫療法
抗原に少量ずつ曝露し、免疫寛容を誘導します。
原因抗原に対する根治的治療に近い方法です。本治療法は私が最も推奨するものです。当院でも7年前から始めており、多くの花粉症患者さんの治療を実施しております。特に小学生以上のお子さんは将来がありますのでこの治療をいち早く始めることをお勧めします。本治療を開始すると次の花粉時期にはかなり症状が緩和され、年々その効果は大きくなっています。約半数の方は抗アレルギー薬が2年目以降には不要になっております。治療は5年続けると終了となり、効果は持続します。治療を希望される方は、本治療を行っている医療機関が公開されていますので近隣の医療機関を探して受診されてください。トップ |
なお、花粉症の治療開始時期は花粉の時期が終了した6月以降、12月ころまでとなります。
詳しくは下記サイトをご参照ください。舌下免疫療法とは|舌の下(したのした)で行う鳥居薬品の舌下免疫療法専門サイト