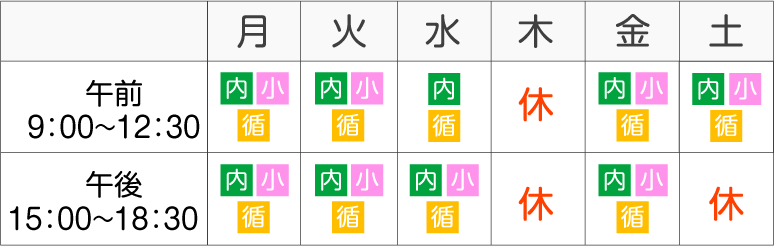- 保険医療内容見直しによる医療費削減の検討
現在の高市政権は維新と連立の形をとりました。その維新の猪瀬議員は以前から医療費削減についての提案を国会に提出しています。その主な内容は、保険診療で扱っている医薬品の一部をOTC(薬局で自費で購入できる市販薬)として扱い、保険がきかなくなるようにする、というものです。ターゲットに挙げられているのが湿布薬です。現在一回の外来診療で出せる湿布薬は以前よりは制限されていますがまだ63枚まで処方できます。これをOTC扱いにしようというものです。また、保険診療でもOTCでも販売されている共通の薬は保険からはずすというのも提案されており、これは主に花粉の時期に大量に出回るアレルギーの薬が含まれます。その他、風邪などありふれた病気に対してセルフメディケーションをより普及させるというシステムも導入しようとしています。これにより診療所通院を減らす効果があります。米国ではよくあることですが、診断までは医療機関で行い、その後の薬は薬局で購入して自費で対応してもらうという方法です。医師はOTC薬を記入した紙を患者に渡し、「これを薬局で購入して服用するように」と提案します。薬局では薬剤師がいるので関連する薬の提案もできるでしょう。患者さんとしては処方箋を出しに薬局に行くのではなく、OTCカウンターにもっていくというイメージです。もちろん薬代はやや高額にはなるかもしれません。このようになれば自然とかぜくらいで医療機関を受診する人は減ってくるかもしれません。現在もインフルエンザやコロナ感染の抗原検査が薬局で購入できますので、外来診療の一部をセルフメディケーションが担っているとも言えます。
- 医療内容の適正化による医療費削減
保険診療は月々医療機関が医療内容をすべて申告して診療報酬を得る仕組みで、不当な医療を行っている場合には診療報酬がその分削られています。しかし、現実には「やらなくてもよい医療」が行われているのも事実です。循環器領域は特に医療費が莫大に使われています。それは高額な医療材料が使われており、それが過剰な医療であっても心臓の治療という名目ですから比較的緩い適応でも査定されません。しかし、以前ステント治療は野放図に行われていましたが、最近はエビデンス重視で心筋虚血が証明されないステント治療は診療報酬が査定される傾向にあります。これはほんの一例ですが、高額医療がしばしば過剰診療に結び付く例は思いつくだけでも数多くあり、それらが適正化されればかなりの医療費削減になると思われます。
- 適材適所の医療分散
前記の過剰な高額医療の実施は、基本的に専門家がなるべくリスクを少なくしたいという思いから行われているのですが、一方で、患者を獲得するとか病院の利益のために行われている場合も少なくありません。これは同じ医療圏内に複数の医療機関があって、それらが競争するあまり、高額医療機器を導入したり、似たような高額な医療を提供したりすることになります。これからはある程度、厚労省などが高額医療や救急医療などを適材適所に配置することも検討した方が良いでしょう。それにより無駄な医療が削られる可能性があります。病床数を減らすことも必要でしょう。現在、地方などでは赤字経営の病院が増えていますが、少子高齢化に伴い人口が特に地方で減っていることが原因となっています。高齢化は進んでいますがそれ以上に病院が多く、やがて高齢者も減少すれば経営も成り立たなくなるので自然と病院は淘汰されていくと思われます。その前に病床を強制的に削減させるのも経営的にも理にかなっています。これにより無理やり入院を延長して医療費が増えるという本末転倒な状況は回避できるのではないでしょうか。